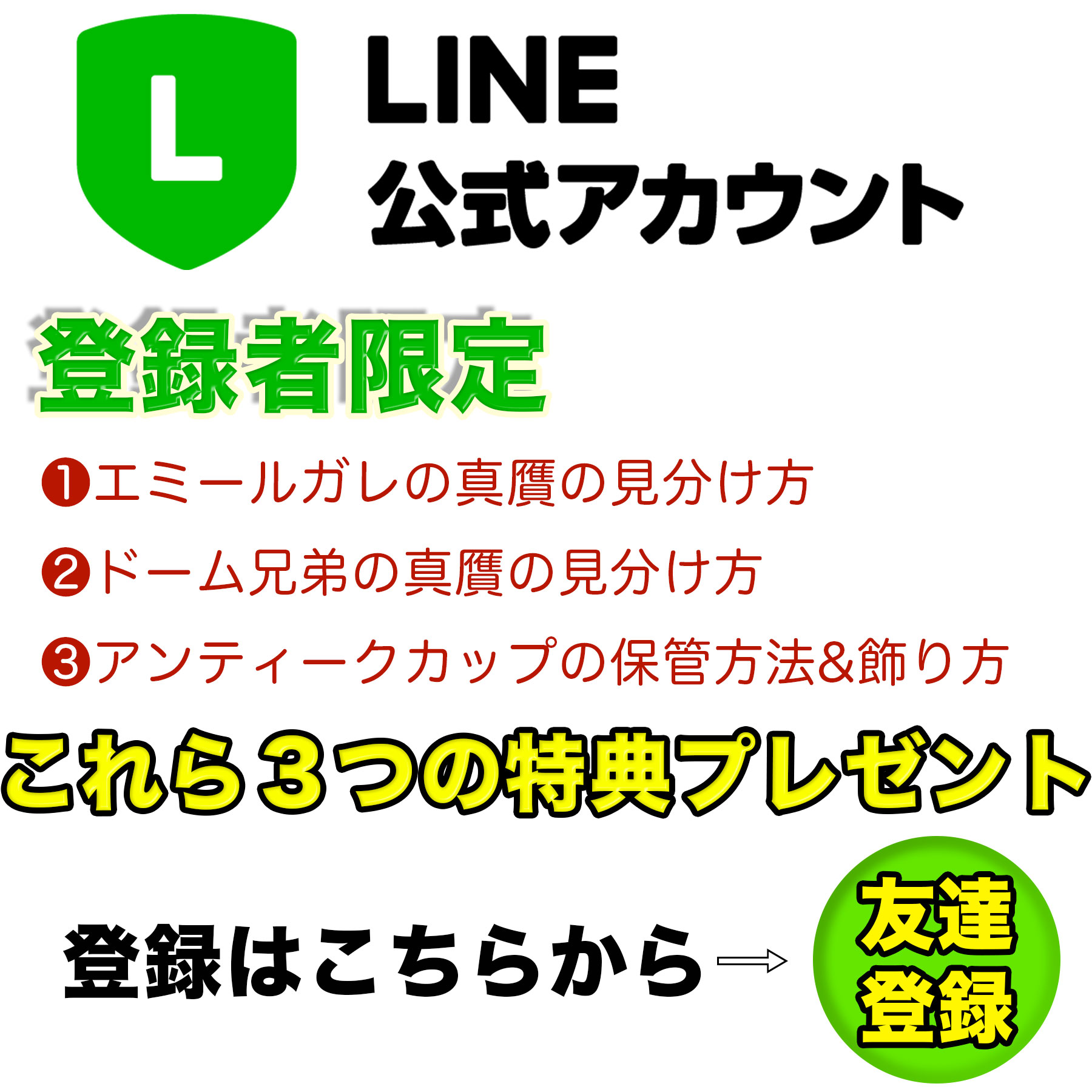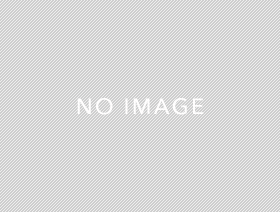オールド・ノリタケと大倉孫兵衛(森村組)
目次
雑貨の仕入れに関して右に出るものはいない
日本ではじめて直輸入というものを成功させた商社と言えば、「森村組」です。
森村組は、ニューヨークで森村ブラザーズという名前で店を構えていました。
当初、その森村ブラザーズで取り扱っている商品は、観光用のお土産のようなささやかなものでした。
蒔絵や印籠、すだれに、日本人形、根付、土瓶、日傘、うちわ、提灯、屏風といったものを取り扱っていたのです。
こうした商品は、全国各地から集める必要がありました。
しかし、当初森村組には、東京に森村市左衛門。ニューヨークには弟の豊の2人しかいなかったのです。
そんな人手不足の森村組に最初に力を貸したのが、大倉孫兵衛だったのです。
その頃、孫兵衛は東京日本橋に「大倉書店」という出版社を経営していました。
もともと、孫兵衛と市左衛門は友人同士でした。
それだけではなく、孫兵衛の亡くなった前妻の兄でもあったのです。
日本を貿易立国にするためには、重要な事業を義兄が行っているということを知った孫兵衛は、出版社を経営しながらの片手間ではありましたが、森村組の手伝いをすることにしたのです。
孫兵衛は、すぐに森村組一本で仕事をするようにしたわけではありません。
「大倉書店」の店主として、森村組を手伝いはじめてからも、およそ20年間努めていたのです。
それだけではなく、孫兵衛は、現在の大倉二幸の前身でもある「大倉孫兵衛洋紙店」までもを始めたのです。
こうした中で、森村組はだんだんと事業を拡大させていき、従業員数も増えていきました。
しかし、仕入れという分野に関しては、どれほど従業員数が増えても孫兵衛の右に出る人はいないというまでに、孫兵衛はベテランとなっていたのです。
孫兵衛は、森村組の手伝いを始める前から日本の特産品に関してはかなり深い知識があったようです。
その理由としては、孫兵衛が出版していた「大日本物産図会」という錦絵のシリーズものです。
政府は上野公園を会場として「第一回内国勧業博覧会」は明治10年(1877年)に開催しました。
このとき、孫兵衛は全国各地の特産物製造風景の錦絵をおよそ150点も記念品として、会場で販売していたのです。
その錦絵の一部を紹介すると「甲斐国葡萄培養之図」、「千島国海驢採之図」、「近江国浜蚊帳輸出図」、「陸前国養蚕之図」、「山城国宇治茶製之図」、「下総国醤油製造之図」、「備後国畳表ヲ製図」というようなものがあります。
この錦絵は、三代目安藤広重の作品です。
しかし、絵師と呼ばれる実際に絵を書く人間だけでは、このような絵を書くことはできません。
実は、同行者が絵師に情報をしっかりと伝えるために、多くの知識を収集しておかなければ、絵師に版画の下絵を描かせることはできないのです。
このようなことから考えても、孫兵衛は日本の特産品に関して、かなりの知識を持っていたと考えられます。
コーヒー茶碗の製造に成功
明治9年(1876年)の秋から、森村組はアメリカへの直輸入をはじめました。
しかし、ある程度まとまった数の陶磁器を輸出の商品として取り扱うようになったのは、明治14年(1881年)からのことでした。
その輸出の最初の製品となったのは、御神酒徳利でした。
これは、孫兵衛が大阪の問屋で仕入れたものです。
アメリカ人は、これを花瓶を誤解してしまいましたが、喜んで買われていたといいます。
その売上の良さから、森村組は主力商品を新品の陶磁器へと絞っていくのです。
そのことにより、孫兵衛の興味や関心も陶磁器へと向くようになりました。
しかし、時が経つにつれて、陶磁器の需要もアメリカの中で満たされていってしまい、売上高が鈍るようになってしまいます。
ですから、森村組のニューヨーク店にいる森村豊は、日本の東京本店に対して「アメリカ人が日常使用することのできるコーヒー茶碗を作ってほしい」という要望を出すのです。
これは明治16年(1883年)の出来事でした。
現在では、考えられないことではありますが、当時の日本において、コーヒー茶碗を焼くということは、不可能なことだったのです。
なぜならば、それまで日本には取っ手のついている茶碗などありませんでした。
ですから、そんな茶碗を焼いたことのある経験者もいなかったのです。
一般的に洋物の食器は日本のものに比べて、とても薄いのです。
コーヒー茶碗はもちろん、受け皿も薄いので、日本人にはその薄さに焼くことができませんでした。
この森村組はじまって以来の難題に、立ち向かったのは、ここでもやはり孫兵衛でした。
森村組には、彼以上に「できる」人間がいなかったのではないかとも言われています。
孫兵衛はまず、コーヒー茶碗の見本を手に入れるところから始めます。
そしてその見本を手に、京都府の粟田や、愛知県の瀬戸を訪れました。
名工たちの窯場をめぐっては、粘り強く交渉を続けたのです。
しかし、そんな見たことも焼いたこともないものを、引き受けてくれるところはありませんでした。
孫兵衛は、仕方なくニューヨークに対して「申し訳ないが、コーヒー茶碗を作ることはできない」という連絡をします。
ですが、ニューヨークにいる森村豊は納得しませんでした。
「西洋人にできることが、日本人にできないはずがない。どうしても作れ」と、再度要請するのです。
仕方なく、孫兵衛は再度この難事に立ち向かうことを決意します。
窯場をめぐりながら「これを作ることができたなら、何万個という数の注文を出す」とまで言ったのです。
そしてついに、引き受けてくれる窯場が現れます。
それが、瀬戸にある陶工川本枡吉でした。
そして、川本の手で日本で第一号のコーヒー茶碗を完成させることができました。
しかし、その茶碗は九谷焼の美しい絵付がされてはいましたが、生地の色はねずみ色、ボテボテとした厚みがあり、取っ手は軽いというようなとても、満足のいく出来ではありませんでした。
さらに、コストの面でも受け皿を含めると80銭から1円50銭(現在でいうと8000円から1万5000円)もかかってしまったのです。
にも関わらず、ニューヨークでそのコーヒー茶碗は大変好調な売上となりました。
そのことにより「今度はコーヒー用の砂糖入れとミルク入れを水差しを作って送れ」という注文が入ったのです。
この注文にも、川本は見事に答えて見せ、ニューヨーク店を再度喜ばせることに成功したのです。
孫兵衛の創案である盛り上げ手法
このようにニューヨークからの無理難題をなんとかクリアしていくうちに、森村組の陶磁器製造部門は、たとえどんなに難しいデザインであっても、作ることができるようになっていました。
結局、生地の多くは最大の取引先でもあった「春光」を含め、瀬戸の窯元で焼かせることになりました。
そして、それを絵付のために東京や京都へと輸送したのです。
そのようにして、完成したものを横浜や神戸から輸出するというルートが確立されていきました。
森村組の輸出品の中で、陶磁器が占める割合が7割を超えたのは、明治22年(1889年)から明治25年(1892年)の間の頃でした。
次第に、森村組のニューヨーク店での売上も上昇していきます。
そしてとうとう、明治22年には、年に45万ドル(45万円)もの売上となっていたのです。
このようにして、森村組は雑貨類のみを取り扱っていた輸出商社から、次第に陶磁器メーカー兼輸出商社へと大きく移行していったのです。
伊勢本一郎は明治26年(1893年)に森村組に入っています。
そんな伊勢本は、コーヒーセットの他に「難しい形のもの」として、ケーキ・セット、ディナー・セット、薬味セット、朝食セット、キャンディー・ボックス、前菜皿、ボンボン皿、花瓶、植木鉢、額皿、灰皿、ランプ台、煙草用具、化粧セットというようなものをあげています。
そして、明治17年(1884年)頃から抱えていた下請け絵付工場の中でも、当時発注をしていた代表的なところと、その特徴としては、次のように挙げられます。
安立工場(東京)・・・円子ぼかし金盛り小菊(円子はピンク色のこと)
河原工場(東京)・杉村工場(東京)・石田工場(京都)・・・地色に玉子茶ぼかし(ぼかしは、一筆で濃いほうから薄くすることの意味)金盛り粟穂に小菊。
西郷工場(名古屋)・・・水金唐子(中国人の子供が遊んでいるような絵)
藤村工場(東京)・・・金ダミ白枝桜(ダミというのは、模様を一色で全体的に塗ること)
伊勢はそれだけではなく、オールド・ノリタケ最大の特徴でもある金盛りは大倉孫兵衛が考案したものであると言明しています。
伊勢は金盛りの絵に関して、孫兵衛創作のエッチンの力によるものと言っていますが、彼の言うエッチンというのは、正しく言うとイッチンのことです。
画集の出版
孫兵衛は森村組で、生産部門を担当している責任者という立場にありました。
しかし、その一方で、大倉書店という出版社の経営者という立場にもあったのです。
明治の時代、大倉書店は錦絵を出版する代表的な版元でもありました。
孫兵衛は経営者という立場だけではなく、編集や画工までをも担当していたのです。
孫兵衛が抜群に質のいい錦絵を刊行していたということは、疑いのない事実です。
大倉出版が版元として出版した錦絵の中でも、1番多いのが明治時代の錦絵と言えばといって、必ず名前が出てくる2人の巨匠でした。
それが、三代目安藤広重と月岡芳年の2人です。
しかし、面白いのはそれだけではないのです。
版元孫兵衛の出す錦絵や絵本の中には、「編集兼・出版人 大倉孫兵衛」という文字や「画工孫兵衛
」という文字が明記されています。
ここで明記されている「画工」という言葉の意味ですが、それは絵師、彫師、刷師を直接監督した錦絵版画における最高責任者という意味でもあるのです。
版元孫兵衛において、もう1つ重要なことがあります。
それは、孫兵衛が大変優れた地図を出版していたという事実です。
その出版されていた地図は、現在でも大変貴重な学問的資料として活用されています。
その、地理的学問の資料として、役立っているのが明治9年に出版された「開明東京新図」と、そのほかの東京市街地図類です。
孫兵衛は、これらの地図を出版するときも、大変な熱の入れようだったようです。
なぜなら、それらの地図の奥付には「編集兼出版人・大倉孫兵衛」もしくは「著者兼印刷発行人・大倉孫兵衛」と記されているからです。
これらのことから、孫兵衛は単なる経営者というわけではなかったということが、よくわかります。
孫兵衛は職人的気質を持った人間だったのです。
そして、その気質は森村組において、遺憾無く発揮することができたのです。
それは社主でもある森村市左衛門に次ぐ経営上のナンバー2という立場にありながらも、孫兵衛は生産の現場で職人たちとものづくりに没頭していたところからも、うかがい知れます。
陶磁器の絵付に関して言えば、もう1つ決定的なことがあるのです。
それは大倉書店が、絵付の下敷きとしても利用することができる画集を多く出版していたという事実です。
幸野楳嶺の「楳嶺百島画譜」をはじめとして、「出版人 大倉孫兵衛」と明記されている画集はおよそ16点にもなるのです。
明治政府は殖産興業政策を推進していました。
それは輸出貿易を盛んにするためでしたが、孫兵衛の出版の意図はそのための工芸運動を強力にバックアップすることと、自社の絵付下請け工場のための参考資料となるものを揃えるためでもあったのです。
孫兵衛の出版していた画集の広告には、下絵には欠かすことができないといった文言を含んだ宣伝文が多くみられました。
明治14年(1881年)から明治25年(1892年)にかけて刊行された画集ですが、下請け絵付工場が孫兵衛の指揮において森村組専属となっていた時期とちょうど重なる時期でもありました。
西洋の筆と絵具の使用
孫兵衛が下請け絵付工場の監督をしていたという事実は、大正4年5月15日号の「実業之世界」でもわかります。
そこには、「日本陶器を世界に知らしめる余の苦心」という孫兵衛自身の回顧文が掲載されているのです。
これは、日本陶器が設立される10年以上も前である明治26年(1892年)に孫兵衛が、シカゴで開催されたアメリカ大陸発見400年記念の万国博覧会を見学するためにはじめて船で海外旅行をしたときからのことが、この回顧文のスタートとなっています。
探し歩いた原土
ニューヨークにいる森村豊から「アメリカのどの家庭でも必要としているディナー・セットの製造をしてほしい」と依頼があったのは明治27年(1894年)のことです。
これを成功させることができれば、森村組の将来は安泰ということは明白でした。
しかし、それはとても大きな難題でもあったのです。
なぜなら、ディナー・セットとなれば生地の色は純白でなくてはいけませんし、材質も硬くなくてはいけません。
日本のやきものでは、存在しなかった純白硬質磁器をつくる必要が出てきたのです。
けれど、そんな難行に率先して関わろうとする日本人などどこにもいませんでした。
結果的に大倉孫兵衛がたった一人で、この大きな挑戦に挑んでいくことになるのです。
これまで、大倉書店の経営なども行いながらのことでしたが、そのときにはすでに大倉書店と大倉孫兵衛洋紙店は義弟たちに経営権を譲っていました。
ですから、孫兵衛はこの問題に全力をあげて取り組んでいくことができたのです。
孫兵衛がディナーセットを完成させるまでには、なんと20年という長い年月がかかっていました。
その間、孫兵衛は東京工業大学の手島校長を訪ね、この大学で窯業を学び、陶器学校の教師を当時の岐阜県多治見でしていた飛鳥井幸太郎を紹介してもらうことができました。
孫兵衛は飛鳥井に森村組で働いてほしいと依頼し、飛鳥井も快諾をしています。
このとき、明治29年1月。
森村組ははじめて専門の技師を雇うことができたのです。
しかし、どれほど失敗を重ねても、純白のやきものは出来上がることがありませんでした。
このままでは、何度繰り返しても成功しないと感じた孫兵衛は、飛鳥井を海外貿易練習生という資格でドイツに明治30年2月から明治31年9月まで留学させることにしました。
そして、飛鳥井が帰国してから再び、純白のやきもの作りに取り掛かりますが、やはり何度行っても成功はしませんでした。
しかし、そんな孫兵衛に僥倖とも言える出来事が起こります。
それは明治35年(1902年)のことでした。
森村組の名古屋支店に2人のイギリス人がやきものを買いにきたのです。
技術を盗む
その2人のイギリス人はローゼンフェルド兄弟でした。
彼らの父親は陶磁器工場の経営者であると、孫兵衛は知り、2人に近づき悩みを相談するのです。
そして工場見学することを許された孫兵衛は、明治36年(1903年)の春に飛鳥井と息子である和親を連れて現在のチェコ、カルロビ・バリであるオーストリアのカルルスバートにある陶磁器工場を見学することができました。
しかし、見学に許された時間はたった1日だけ。
そのため、孫兵衛は病気を装うことにしたのです。
そして、病気が回復するまで和親と飛鳥井の2人を工場で働かせることに成功しました。
2人がしっかりと最新の陶器焼成法を学んでから、無事に三人はその場を去ることができたのです。
それから三人はベルリンへと向かいます。
ドイツ国立陶土工業化学研究所を訪ねるためでした。
結果は、極めて良好なもので、ついに純白のやきものを焼成する見通しを立てることができたのです。
その頃、日本ではディナー・セットを大量に製造するために名古屋に大工場を建設することが決定されていました。
そこで孫兵衛らは、明治36年の秋にドイツのチューリンゲンにて最新式の機械を購入、工場の設計に関する手配もすべて終了させてから帰国の途につきました。
「日本陶器合名会社」が名古屋市の郊外である鷹場村大字則武に設立されたのは明治37年(1904年)の一月一日ことでした。
代表社長となったのは大倉和親です。
石炭焚による洋式磁器焼成窯の第一号に最初の火が入ったのは、この年の11月のことでした。
しかし、新工場が稼働を始めたにも関わらず、ディナー・セットは完成することができませんでした。
それは、ディナー・セットの中でもっとも大きな八寸皿(直径24センチ)が、中央部分が焼くと垂れ下がってしまい、商品とならなかったからです。
その試行錯誤は、大正3年(1914年)6月までという大変長い年月かかってしまいました。
あまりの長引き様に売る側の立場である、森村市左衛門と作る側の立場である、大倉孫兵衛が大喧嘩をしてしまったということもありました。
明治43年10月には技師長の飛鳥井幸太郎に責任を取り、辞めてもらうという事態にもなりました。
さらに、社長であった大倉和親自ら再びカルルスバートの工場を訪れ、陶磁器つくりの見学もしました。
こうして、20年もの時間をかけて日本製のディナー・セットは完成するのです。
日本陶器のディナー・セットは年を追うごとにどんどん、生産量が増えていきました。
「ノリタケ」というブランド名はこのようにして世界中へと広がっていったのです。